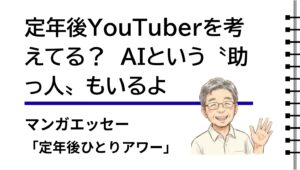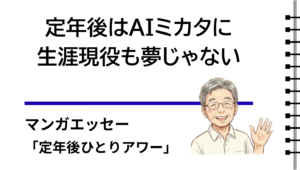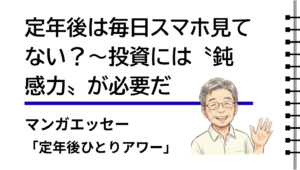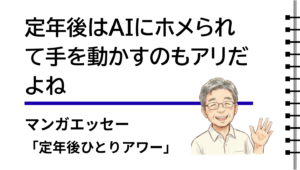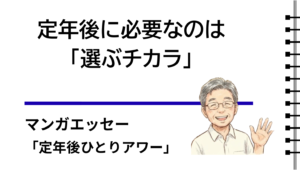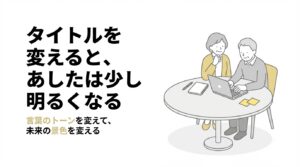お金の不安を減らす近道は、難しい投資テクニックではなく「見える化」と「順番」です。この記事では、初心者でも今日から実践できる金融リテラシーの4本柱――①家計管理 ②生活設計(ライフプラン)③金融・経済の基礎知識 ④外部の知見活用――を、資産形成や老後資金にも役立つ手順で解説します。
記事のエッセンスをショート動画でもご覧いただけます
チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします
家計管理:収支を見える化して貯蓄率の土台を作る

家計簿は金融リテラシーの出発点。まずは「固定費・変動費・貯蓄」の3分類でOKです。固定費(通信・保険・サブスク)は一度見直すと効果が長続き。変動費は上限を決め、残りを先取り貯蓄に回します。家計簿アプリで口座やカードを連携すれば、自動記録で継続しやすく「どこにムダがあるか」が一目瞭然になります。目標は貯蓄率を段階的に引き上げること。最初は5%から、慣れたら10~15%を目指しましょう。
生活設計(ライフプラン):必要額を〝期限つき〟で逆算
-1024x574.png)
結婚・子育て・住宅・老後などのイベントを年表にし、「いつまでに・いくら必要か」を数字で置きます。例=教育資金○年後に○万円、老後資金は65歳までに○万円‥‥など、金額が見えると毎月いくら貯めれば良いかが決まります。
短期(~3年)は安全性重視、長期(10年以上)は時間分散を効かせる――と目的別に器を分けると、ぶれない家計運営につながります。
金融・経済の基礎を〝レシピ化〟して覚える

銀行預金は流動性、保険はもしもの備え、投資信託は分散と長期で資産形成――役割の違いを押さえましょう。わからない商品は買わない、手数料は小さく、目的・期間・リスク許容度で選ぶ‥‥が基本レシピです。特に投資信託は積立・分散・長期の3点セットが初心者向け。家計管理とライフプランで余力を作り、その範囲でコツコツ積み立てることが不安を小さくします。
外部の知見を味方に:相談する勇気も〝資産〟

すべてを一人で判断する必要はありません。ファイナンシャルプランナー(FP)や銀行員に相談し、セカンドオピニオンで判断の偏りを減らしましょう。相談前に、家計簿の概況、イベント年表、質問リスト(保険は必要?投資額の目安は?)を準備すると、短時間で的確な提案を得られます。
7日間ミニ・アクションプラン

- Day1 固定費を洗い出し、不要なサブスクを1つ解約
- Day2 家計簿フォーマット決定&アプリ連携
- Day3 ライフイベント年表を作る
- Day4 必要額を仮置きして月々の目標額に分解
- Day5 保険の役割と保険料をチェック
- Day6 少額の積立(例:月5,000円)を設定
- Day7 FP相談の予約+質問3つを整理
まとめ:順番と継続が、金融リテラシーを強くする
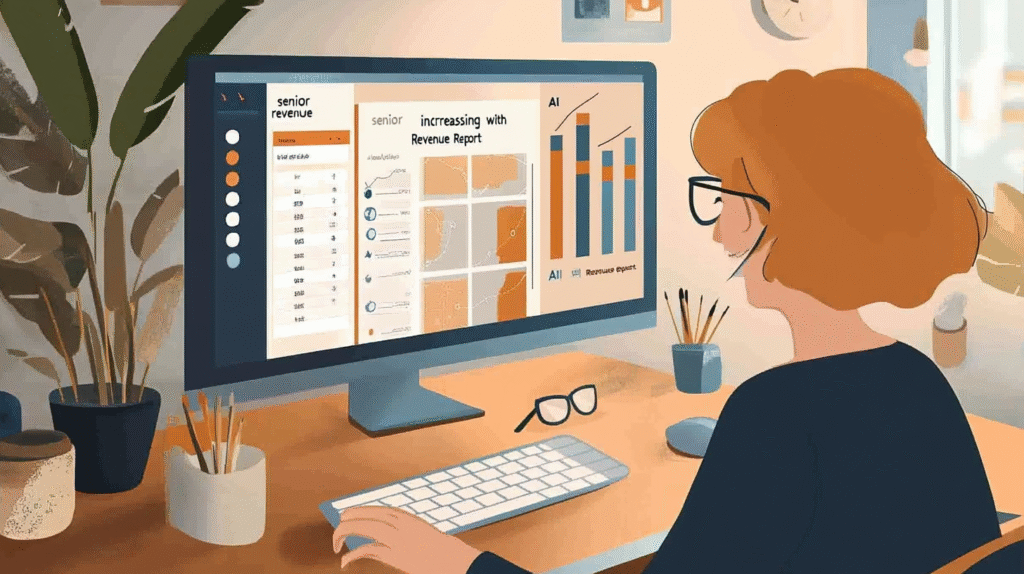
「家計管理→生活設計→基礎知識→専門家活用」という順番で進めれば、家計は確実に整い、投資信託や貯金、老後資金の判断もブレにくくなります。今日の一歩は、小さくても十分価値がある行動です。まずは固定費の見直しと先取り貯蓄、そして7日間プランから始めましょう。あなたの未来の選択肢は、今の一歩から広がります。
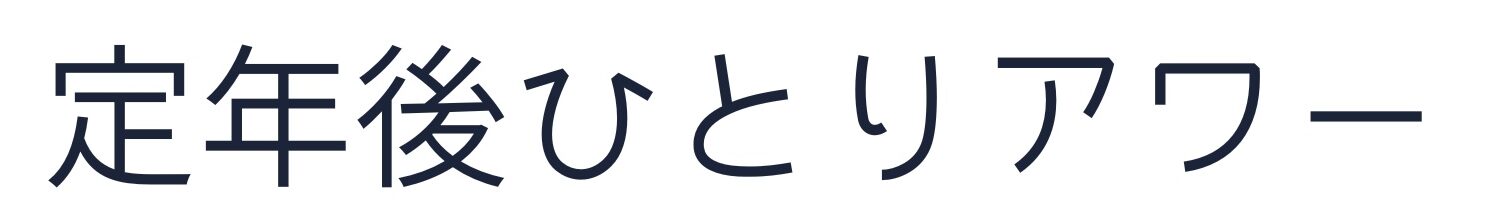
.png)
-300x168.png)